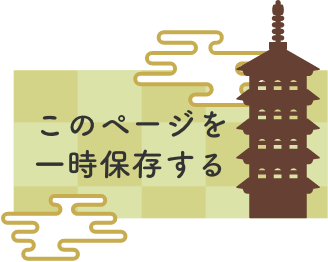利用者負担額について
- [公開日:2025年7月9日]
- [更新日:2025年7月9日]
- ID:125
介護保険サービスの自己負担について
介護保険のサービスを利用したときは,かかった費用の1割~3割を自己負担します。また,施設に入った場合には,費用のほかに食事代や日常生活費なども自己負担となります。
厚生労働省からのお知らせ(平成30年8月改正)
自己負担が高額になったとき
サービスを利用したときに支払う自己負担額が一定の上限額を超えたときは,その超えた額を申請により高額サービス費として払い戻します。この場合の自己負担額には,施設における食事代や日常生活費その他保険給付外のサービスに係る費用は含まれません。同一世帯に複数の要介護者などがいるときは,世帯全員の自己負担額を合算します。
| 区分 | 負担上限額 |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の人 | 93,000円(世帯) |
| 町民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の人 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が町民税非課税の人 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が町民税非課税の人のうち ・老齢福祉年金を受給している人 ・前年の合計所得金額+課税年金収入額が年間80万9千円(※)以下の人 | 24,600円 (世帯) 15,000円 (個人) |
| 生活保護を受給されている人 | 15,000円(個人) |
※令和7年8月以降は80万円から80万9千円に変更になります。
厚生労働省からのお知らせ(令和3年8月改正)
所得が低い人が施設を利用したときの居住費と食費について
所得が低い人が施設を利用したときの居住費・食費について、所得に応じた負担限度額が設けられており、超えた分を特定入所者介護サービス費として介護保険から給付されます。
給付を受けるためには、役場福祉課へ申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
なお、有効期限は毎年7月31日までとなるため、引き続き利用する場合は、申請が必要です。
| 所得の状況(※1) | 預貯金等の資産の状況(※2) | 居住費の 負担限度額 従来型個室 |
居住費の 負担限度額 多床室 |
居住費の 負担限度額 ユニット型個室 |
居住費の負担限度額 ユニット型個室的 多床室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 | 550円 (380円) | 0円 | 880円 | 550円 |
300円
|
| 第2段階 世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円(※3)以下の人 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 | 550円 (480円) | 430円 | 880円 | 550円 | 390円 【600円】 |
| 第3段階(1) 世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円(※3)を超え120万円以下の人 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 | 1,370円 (880円) | 430円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 【1,000円】 |
| 第3段階(2) 世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円を超える人 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 | 1,370円 (880円) | 430円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 【1,300円】 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合は対象外)の所得も判断材料とします。
※2 【預貯金に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。
※3 令和7年8月以降は80万円から80万9千円に変更になります。
・第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象になります。